King Gnuの楽曲は、そのほとんどを常田大希が作詞作曲を手掛けており、その歌詞は文学的で深みがあり、社会に対するメッセージ性も含んでいます。King Gnuは2019年にメジャーデビューを果たした4人組のロックバンドです。
楽曲はロックだけでなく、かなり広いジャンルをカバーしておりR&B、ジャズ、J-POPなどの要素を取り入れながら聴き馴染みやすい曲が多くなっています。曲中に転調したりアレンジされることもあり、楽曲に対するこだわりが強いバンドのようです。
歌詞は日本語によるフックが意識されており、曲よりもフレーズのほうが強く印象に残っていることもあるのではないかと思います。
この記事ではKing Gnuの初期の代表曲を中心に歌詞の分析を試みます。
Vinyl
2017年10月リリース曲。「Vinyl」はKing Gnuの前身バンドのSrv.Vinci時代にリリースされたアルバム「トーキョー・カオティック」の収録曲を原曲にしています。
退廃的な雰囲気のある曲で、70年代井上陽水などのおしゃれな世界観も思い起こさせます。
歌詞の表面では抑圧された感情の爆発と、自由への渇望を力強く表現しています。ビニールに喩えられる束縛からの脱却、そして「遊び」を通しての自己解放が中心的なテーマになっているように見えます。
個人的に常田大希の詩作は直接的な表現が多いという印象を持っていたのですが、この初期の作品では抽象性が高くなっており、ウラ側の意図を読む必要もありそうだと感じました。
オモテ側の揺れ動く視点
歌詞を読んで最初に気づくのは視点が男女の間を揺れ動くということです。口調などで判断するしかありませんが、何度か繰り返される「“さよなら、愛を込めて”」などはどちらの言葉なのか不明にしているところもあります。
男性側の視点では「ビニール」という比喩を通して表現される、何らかの抑圧からの脱却への強い願望が見えます。この「ビニール」は、社会的な期待、恋愛関係における縛り、あるいは自己抑制と解釈します。彼は「ビニール」を脱ぎ捨てて、自由奔放にそして自暴自棄ぎみに「暴れ」たいと願っています。
女性側も 「暇つぶしには飽きたのよ 纏ったビニールを脱がせたいの。」という一節から、男性の解放を望んでおり、現状打破への強い意志が見えます。
そして「さよなら 愛を込めて」は別れを告げる言葉でもありますが、関係継続への未練がありながらもお互いに相手を思いやった真摯な決断の言葉として表現されているのでしょう。
歌詞に出てくる「遊び」は単なる娯楽を言っているのではなく、人生そのものを「遊び」として捉えて、既存のルールや価値観に縛られず、自由に生きようとする姿勢なのでしょう。 「遊びきるんだ、この世界」は、この「遊び」という生き方を貫く意思ですが、社会的な規範からは逸脱してゆく部分もあるように感じます。
特に男性側の心情には激しい感情の揺らぎがあり、内面の葛藤が自問自答で表現されています。終盤の「最後の最後には ニヤリと笑ってみせる」と葛藤を乗り越えて意思を貫いてゆく決意と自信が感じられます。
歌詞ウラ側にある性描写
ウラ側は基本的に個人的な想像になるのですが、この歌詞においては意図的に構成されていると断言してもいいでしょう。
「Vinyl」は歌詞の全体が「性描写とその後の生命の神秘」のメタファーになっていると思います。「ビニール」は要するに避妊具なのでしょうし、MVの途中ではビニール袋を被ってメンバーが巨大な白頭になっていました。
King Gnuはアーティストとしての意識の高いバンドだと認識していたのですが、そんな彼らもシモネタ曲から始まっているというのも面白いと思います。
Prayer X
2018年9月リリースの「Prayer X」はアニメ「BANANA FISH」のエンディング曲になっています。
信じられる何かを探す
「BANANA FISH」の原作漫画やアニメは見ていないのですが、あらすじを読むかぎりかなり殺伐としたハードな内容であるようです。このタイアップにより楽曲の内容がどの程度リンクしているかは不明ではあるものの絶望的な雰囲気は共通しているのだろうと思います。
「Prayer X」は社会に生きる人々の不安や葛藤、そしてかすかな希望を描いています。どこか哲学的とも言えるような深みが感じられる作品になっています。
この歌詞の中心となっているのは繰り返される問いかけ「一体全体何を信じればいい?」でしょう。この詞中人物は刹那に感じられる人生の中で寄りすがる何かを探しているように見えます。おそらく人との信頼関係や恋愛関係において裏切られる経験をしたのだと考えられます。
感情の奔流を抑えていた「胸に刺さったナイフ」は何か決定的な言葉、もしくは出来事。それを反芻してしまうことは悲しみや無力感が溢れ、深い絶望と苦しみを味わうことになるのでしょう。
人生の儚さを感じながら、信じられるものを探すことはどこか矛盾した部分があるような気がします。「一体全体何を信じればいい?」は何かを信じることが生きてゆくためには必要であるということが前提にあり、さらに裏返すと信じられる何かを欲している人物は生きる希望を希求しているからです。
Slumberland
2019年1月リリース曲。
King Gnuの覚醒
「Slumberland」の歌詞では、東京という大都会の現実の風景とメディアに映し出される風景に乖離があり、それが虚構のように見えるという認識がまずあるのでしょう。
そうした虚構に浸った人々はSlumberland(眠れる国)の住人であり、ロックンローラーであるKing Gnuはそこから目を覚ませと歌っている。
テレビに代表されるメディア産業への皮肉と言うより批判が入っており、この曲においてKing Gnuのスタンスが明確に打ち出されたと言えるでしょう。King Gnuが本物のロックンローラーとして、アーティストとして新規に再生された瞬間でもあると思います。
夢の国の住人に目を覚ませというのは、浮かれるのやめて現実を見つめ直せと言っているのですが、現状からの変化を求めているということです。ロックンローラーとしてはそれぐらいしかできないけどねという謙遜を付け加えてはいますが、現役のアーティストから放たれるメッセージとしては強い意思を感じます。
ヌイグルミの反乱
擦れて溶けたビロード
からは露わ傷を披露
けれど血は出ぬ我が身
中身が空っぽの強み、伴う痛み
来た道振り返り生まれる弱み
寄せては返す人の波
それでも繰り返す日々の営み
擦れて溶けたビロード
見事に露わ傷を披露
けれど血は出ぬ我が身
中身が空っぽのお詫び
のらりくらり都会暮らし
この曲の歌詞で残る問題はこの韻律の多いラップパートになるでしょう。ビロードは布地の一種で、ここでの主体がヌイグルミであるかのように描写されています。それもかなり傷んだヌイグルミです。全体の文脈からは少し外れた感じで置かれているのが意味深なのですが、うまく意図は読み取れませんでした。
MVではパペットが出てきてテレビ番組の出演者を操っているように表現されています。ここから少し強引な仮説としては、夢の国の住人でもある現実の都会に暮らす人々を傷を負って中身を失った人形やヌイグルミに見立てることで、その反乱の表現にしているのかもしれません。
白日
2019年2月リリースの「白日」はKing Gnuの代名詞になっていると言っても良いでしょう。ドラマ「イノセンス 冤罪弁護士」の主題歌でもあり、白日には潔白という意味もありますし冤罪がウラのテーマにあるのかもしれません。
人生の不条理さを描く
「白日」の歌詞は「後悔」と「諦念」を繊細な言葉で描き出した名曲だと思います。シンプルな言葉で複雑な人間の感情と、人生への深い覚悟が表現されています。
歌詞は、まず誰かを無意識のうちに意図せず傷つけてしまう罪を犯してしまった人物の描写から始まります。彼は過去の過ちに罪悪感と後悔の気持ちを抱いています。また同時に失った過去への未練もありながらも、新しい明日へ歩みだす覚悟を決めようとしています。
彼は誰かとともに生きるためには、今の自分を曲げて新しい自分になる必要があることを痛感しており、そうなることができればやり直せると期待を持っています。
春風に象徴される変化は、雪に象徴されるまっさらな世界を経験し、生まれ変わらなければなりませんが、過去の過ちという現実からはどうやっても逃れられないという事実にも直面しています。
いっそ雪による真っ白な世界に留まって全てを洗い流せたら良いと願うのですが、過去と決別し明日へ歩き出そうとする諦めの気持ちも生まれはじめています。
冤罪説の可能性
さて、歌詞ではこの人物の犯した罪がどのようなものであったのか、不自然に感じるくらいに具体的には描写されません。「曖昧なサインを見落した」だけで罪となってしまうのは不条理な話のようにも思えます。
ここはやはり冤罪が歌詞のウラのテーマとしてあり、作中人物はほとんど難癖のような罪を引き受けているとも解釈できるようにしているのでしょう。
主観的には自らの鈍感さを嘆いて悔恨に苛まれてはいますが、客観的に見ると酷い冤罪を被っているだけなのかもしれません。その場合「朝目覚めたら どっかの誰かに なってやしないかな」というのはこの人物の自信のなさ、あるいは主体性のなさを表しているのでしょう。
「それでも愛し愛され 生きて行くのが定めと知って」というフレーズにも人生の不条理を受け入れ、それでも生きていこうとする強い意志を示されていますが、ここでも人生や人間関係の不条理さ自体が強調されているように見えます。
The hole
2019年5月リリース曲。
届かない愛情
「The hole」は切ないメロディーの楽曲で心の傷や孤独、そして他者への深い愛情を表現されています。「穴」という比喩を用いて、心の傷つきやすさと、それを癒そうとする優しさ、そして脆い人間の姿を描き出していると思います。
この曲のMVではずいぶんドラマティックな物語が別に展開されているのですが、歌詞ではシンプルな展開になっています。ここでは歌詞の物語を中心に見てゆきます。
歌詞は比較的平穏な心情を持つ主人公「僕」の視点から始まります。「僕」自信は自分の心の内を冷静に見つめることができる人物のようです。
そこに「僕」が守りたい「あなた」が登場します。「あなた」は不安定な心を持っておりそこに「穴」を持っています。
この「穴」が何を象徴しているのかがこの曲における問題の中心になるのですが、とりあえず何かの喪失感や心の傷、孤独などの総称のように扱われます。
「僕」は必死に「あなた」を守ろうとしており、その「穴」を埋める存在になろうとしますが「あなた」からはそれを受け入れる意思も、生きてゆく意思もあまり感じられないまま物語は終わってしまいます。
「僕」には「あなた」への深い愛情があるのですが、それは一方通行なものであるようです。「あなた」には「穴」が空いたままで、心を取り乱して壊れてしまいそうに脆く不確かです。
歌詞のストーリーとしてはこの構図を描くだけで十分に成立していると思うのですが、「僕」の自己犠牲的な愛情が空回りした感じのままで終わる展開は、余韻や後味はそれほど良くはありません。
「穴」は何を象徴するか
この歌詞の解釈は「穴」をどう意味づけるかで決まってしまうでしょう。もちろん本線は心の傷であり孤独であり喪失感であることも間違いないでしょう。
MVでもそうなのですが、「The hole」というタイトルにしていることからも「穴」は性的関係の存在を暗示していると個人的には想像します。つまり性的な意味を含んだ精神的な融合が意図されていて、その結合点の象徴として「穴」が「傷口」に変換されるということなのかなと思いました。
つまり「あなた」の存在が希薄であるのは既に「僕」と融合を果たしているからであり、抽象的な表現として、おたがいが融合し内包することによって「僕」は「あなた」を「そっと庇って」いるという結末の歌詞になっているように読めます。
飛行艇
2019年08月リリース曲。ANAのCMイメージソング。
なぜ飛行艇か
歌詞を読んだ後に最初に感じた疑問はこの曲のタイトルが「飛行艇」であることです。飛行艇は水面で離着水できるように作られた飛行機の一種ですが、歌詞の内容的には飛行艇でなくてはならない理由はなかった気がしたからです。
「自由自在に飛び回って」いるのはあくまで抽象的な表現になっているので、これが仮に飛行機であったとしても収まりは悪いのですが、あえて飛行艇であるのはそこに何か意図がないと難しい。
この曲はMVが凝っていて、キング・ヌーのお面を被った少年がヒーローになるまでの成長物語になっています。歌詞もそこにリンクしている部分もありますが、どちらかと言えばメッセージを伝えることに集中しています。
歌詞は自由への憧憬と今このときを生きろという主張が中心になっています。自由な発想と冒険心を促して、常識にとらわれず自分の道を進んでゆく意思を持てというメッセージですね。また今この瞬間に生きることに集中して、命を燃やそうと訴えています。
おそらく飛行艇は空を飛ぶための機械であるというより、自由自在に飛び回ることができる船というところからの比喩になっているのでしょう。制約のない自由な世界への憧憬があるのだと思います。
また「代わり映えしない日常の片隅で 無邪気に笑っていられたらいいよな」というのは日常の生活の苦しさから逃れたい気持ちがあり、自由な生き方に憧れる動機の部分を表現しています。
「愚かな杭」は自分の信じる道を貫く意思の強さの表現でしょう。「名も無き風」は社会的評価とは無関係でいることを示し、「清濁を併せ飲んで」は自由に生きるという目的のためには何でも受け入れる覚悟を持つことを言っているのでしょう。
入れたいマン説
貴女の期待に飛び乗って
今夜この羽根で飛びたくて
この大空を飛びたくて
命生まれ 命生まれ
終盤のこのパートは繰り返しのなかに現れるので見逃してしまいそうになりますが、微妙に全体の歌詞のテーマやメッセージからすると意味合いが少し変わっている感じがして気になります。
貴女は誰なのか、その期待とは何なのか、この羽根とは何なのか、命生まれとは何を意味するのか。
性行為の暗喩が入っているだけなのかなと単純には想像するのですが、だとすると常田はそうした要素を絶対入れたいマンということなんでしょうねえ。
傘
2019年11月リリース曲。ブルボン アルフォートCMソング。
レトリックの魔術
「傘」の歌詞は恋人に去られた直後の男性側の様子と心情を描いたシンプルな内容で、あまり深く分析するような要素もないのかなと最初は思ったのですが、何度か読み直すうちにそれほど単純な構造ではないとわかりました。
もちろん歌詞の解釈は多様にあり得ると思いますので、その一つだと思ってください。
まずこの歌詞はサビ始まりになっているので、話の時系列的には「3回目のアラームで」男性が起き上がるところから始まります。この男性には「もっと近づきたい」と感じている意中の女性がいて、彼女と結ばれることが「運命」なのではないかと半信半疑でいます。
男性は仕事をなんとか無難にこなしながら「直行直帰寝落ちる毎日」の生活ですが、通勤途中の満員電車でときおり見かける女性に出会うことだけを楽しみにしています。
繋いだ手確かめた
確かに僕ら此処に居たのさ
寄せては返す波の中を
必死に立っていたんだ
このパートは満員電車で身動きができないなか(おそらく偶然に)女性の手に触れた瞬間を描写していて、人波に揺られながら立ちつくした状態を運命の成就として男性が受け取っている場面なのでしょう。
もちろんその後の展開は「巷に流れるラブ・ソングのように」はいかず、女性は「傘も持たずに」電車を降りていってしまいます。雨で曇った電車の窓ガラス越しに去ってゆく女性を見送ったあと、男性は反対側のガラスに反射する「自分の頼りない背中」を見るわけです。
この解釈は曲解なのかもしれませんが、そう読んでもそれほど違和感がないようには作られていると思います。そうでなければ後半に満員電車の描写が出てくる必然性があまりないからです。いずれにせよ常田の作詞家としての能力が遺憾なく発揮された歌詞なのではないでしょうか。
Teenager Forever
2020年1月リリース曲。ソニーのワイヤレスイヤホンのCM曲。
真っ直ぐな若者応援歌
「Teenager Forever」の歌詞は技巧的な細工やひねりがあるわけではなく、ストレートに若者への讃歌になっています。作者自信の経験も踏まえた今の10代への応援歌として作られた曲だと読めば良いのでしょう。
若者への応援ソングは多くの音楽アーティストが作っていて、いまでは定番のテーマになっていると言えます。そのメッセージは概ね共通しているのですが、それぞれ特徴的なところもあります。ここでは簡単にこの曲を整理してみます。
まず「他の誰かになんてなれやしないよ」は自己肯定や自己承認を促しています。自分のアイデンティティの確立をしようと言うことですね。
「望んだこと全てが 叶う訳はないよ」は人生において全てが自分の思い通りになるわけではないという現実を受け入れて、それでも前を向いて生きていこうという提案。
「いつまでも 相変わらず つまらない話を つまらない中に どこまでも 幸せを探すよ」などの繰り返しのフレーズでは、日常の些細な喜びや人間関係の温かさといった、一見目立たない幸せにこそ人生の真の価値があると言っており、この曲の中心的なメッセージになっています。
他のアーティストによる若者への応援ソングに比べると、King Gnuのものはシンプルで等身大な感じが強く伝わってきます。MVを見た影響もありますが、10代を人生において特別な時間として本当に共感して応援する気持ちが彼らにあるからなのでしょう。
どろん
2020年2月リリース曲。映画「スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼」主題歌
畳み掛けられる歌詞
曲中はほぼ全域でボーカルが入り息継ぎがよくできるなと思うぐらいなので、曲を聴きながら歌詞の内容を把握するのはおそらく無理でしょう。音も多いので音声が聞き取りにくいということもあります。
内容を知るためには歌詞譜を用意して読むしかありません。ただし読んだとしても言葉は重なっているのに何について歌っているのかが今ひとつわからない。この曲に関しては断片的なフレーズからふんわり雰囲気だけ読み取るのが正解のような気もしてしまいます。
サスペンス説
映画「スマホを落としただけなのに」に関連しているとすると、この歌詞はひとつのサスペンスドラマ仕立てになっているのではないでしょうか。
たとえばAパートを読むと、「白黒で単純に割り切れやしないよ」から「正義か悪かそれどころじゃないんだ」までは犯罪者(予備軍?)の目線で書かれているように読めます。正当化して悪ぶろうとしている感じですね。
これは繰り返しのA’パート「散らかった部屋に押し潰されそうだ」から「自分を好きになりたいんだ」までも同様で、不健康で閉じこもった生活の孤独で身勝手な人物が恋愛感情を持ってしまった様子が描かれているように読めます。
つまりこの歌詞の人物「彼」は強い疎外感を感じていて、社会から取り残されて切り捨てられてしまうのではないかという恐怖を抱えています。「いつだって期限付きなんだ 何処までも蚊帳の外なんだ」は「彼」の言葉であり、味方をしてくれた人はいつのまにかいなくなってしまっています。
今日だって
傷を舐めあって
面の皮取り繕って
居場所を守ってるんだ
あなたの事を待ってるんだ
当初はこのパートは家庭でパートナーの帰りを待つ主婦(主夫)のセリフかと思っていたのですが、それだと話がまったくつながりません。
おそらくこれはターゲットとなる女性を待ち構える「彼」のセリフなんですね。その居場所を確保するために彼なりに苦労しているという描写なのでしょう。もしくは文字通り遺体の「顔の皮」の「傷」を取り繕っているとか。
もはや「彼」は社会の不条理に追い詰められてしまい「後には引けやしない」状況にあります。
ここはどこ、私は誰
継ぎ接ぎだらけの記憶の影
煌めく宴とは無関係な
日常へ吸い込まれ、おやすみ
意識の錯綜を経て日常へ戻った後に、誰かに「おやすみ」を言っています。
「どろん」は蒸発する被害者であり「ごろん」と転がります。シリアルキラーの物語。
三文小説
2020年11月リリース曲。ドラマ「35歳の少女」主題歌。
個人的にこの曲は今回はじめて聴いたと思うのですが、なかなかドラマチックな曲で聴き入ってしまいました。
独白小説?
人生を「三文小説」に例えるという比喩ですが、人生の先行きの見えなさ、儚さなどを表現しているのでしょう。人生がままならないものでも、それを受け入れ、何度も書き直しながら生きていこうという強い意志も感じられます。
とはいえ、歌詞の人物が相手の返答や反応もないまま、最後まで独白的に思いを伝える構成になっているのはなんだか不気味な印象があります。そしてそれ自体に何か意図や仕掛けがあるはずです。
植物状態説
あゝ
立ち尽くした
あの日の頼りない背中を
今なら強く押して見せるから
全体的に素直に読める歌詞ですが、唯一意味が取りにくいのがこのパートです。
もちろん「背中を押す」は決断を促すという意味にも取れますが、わざわざ「頼りない背中」と断っています。また「今なら」押せるわけですから、強く押せなかった過去があるはずです。なぜ押す必要があるのかは疑問ですが。
この「頼りない背中」は「傘」でも出てきました。強引に同一人物説も立てられないわけでもないでしょうが、あまり必然性がない気もします。
ともあれ決断を促すという意味ではないのであれば、動作としての背中を押すという意味に取るしかありません。
作中人物は何らかの理由でパートナーの背中を(強くはないが)押した過去がある。想像するに、その結果としてパートナーは植物状態になってしまったのではないでしょうか。人物はその後臨床にあるパートナーに付き添って独白的な呼びかけを続けている。つまりそれがそのまま歌詞になっている。
「今日も隣で笑う」「皺の数を隣で数える」なども病床の横にいる感じがします。小説を書き足すのも三文芝居も本当は二人の空想の人生なのかもしれません。
ちなみに「三文小説」はドラマ「35歳の少女」の主題歌であり、ドラマは10歳の少女が25年眠り続けて35歳の誕生日に目を覚まして、という設定になっています。
King Gnu 歌詞分析まとめ
記事のために安直な気持ちで10曲を選んだのですが、どの作品も歌詞批評するには重量級なので時間がかかってしまいました。King Gnuに関してはこれからも歌詞批評してゆきたいと考えていますので、次からは1曲つづにしたいと考えています。
常田大希詩作の特徴
常田詩作の特徴はいろいろな作品を読んでもなかなか掴めないところがあります。それは楽曲ごとに構成やコンセプトが異なっており、文体やレトリックといった言葉の選び方も変えられているからです。
King Gnu自体が常田と井口のダブルボーカルが作り出す多彩な表現性を持っているのですが、それを支えているのは常田の卓越した作詞能力なのだと思います。それぞれの作品ごとにまったく別の世界が高精細に描かれています。
今回King Gnuの歌詞批評をしてみて驚いたのは、やはり作詞家常田の遊び心のある仕掛けの数々ですね。小説で言うショートショートのようなギミックが仕込まれた作品が多く、それを読み解いていくのは楽しい作業でした。
こうしたギミックのある作品では、楽曲リリース時などの「説明」ではおそらくネタバレが避けられるでしょうから、「説明」にないからと言って、ここで指摘した解釈がすべて大幅に的外れであることもないはずです。いずれにしても楽曲の解釈は聴き手次第ということでご理解ください。
常田詩作がどのような過程を経て生み出されているのかは不明なのですが、歌詞の内容とコンセプトの間にほとんど齟齬が感じられないことから、まずコンセプトから楽曲の世界観がそこに適合するように決められるのだと思います。そこから登場人物、物語などが創造されて、歌詞の構成、使用する言葉の選定と続き、最後にタイトルが本質を突かないギリギリ外れたところを選んで置かれている感じがします。
常田詩作では描かれる価値観や人生観なども十分に思索を経た落ち着いたものになっていて、鑑賞に足る深みがあると感じます。また楽曲で伝えられるメッセージも心に響くものになっていると思います。
歌詞のテーマも基本的にストレートなのが良いところで、メッセージをまっすぐに伝えたければダイレクトに、作品として精緻なものを作るときは技巧的で芸術性の高い歌詞になるという、緩急の使い分けが素晴らしい。
自分には楽曲全体の批評をする能力はないのですが、メロディやサウンド、歌唱も圧倒されてしまうことが多いです。単純に次の新しい曲が聴けるのを楽しみにしてしまっている状態です。
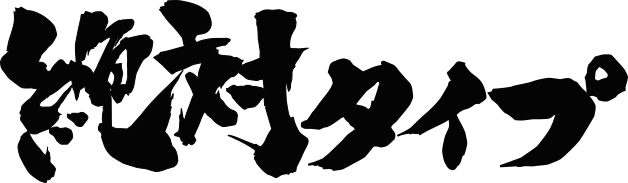



コメント